『投資で一番大切な20の教え』を深く読む
本連載では、ハワード・マークス氏の名著
『投資で一番大切な20の教え~賢い投資家になるための隠れた常識~』を、
全20章にわたって解説・実践していく企画です。
各章の要点をわかりやすくまとめるだけでなく、
私の投資スタイルにどう活かしていくかも一緒に考えていきます。
市場は“効率的”ってどういうこと?
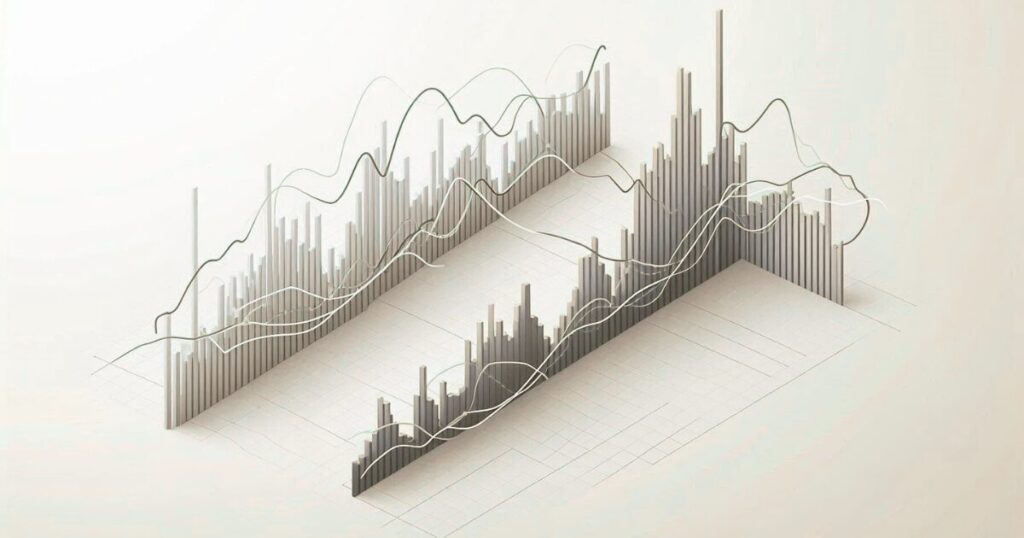
投資の世界ではよく耳にする「効率的市場仮説」。
これは「市場に出回っているすべての情報はすでに株価に反映されており、
誰も市場平均を安定して上回ることはできない」という考え方です。
インデックス投資は、この仮説を前提にしています。
つまり「市場に勝つ必要はない。市場全体に乗っていれば十分」という考えです。
たしかに、長期の視点ではこの仮説はかなり説得力があります。
なぜ“効率的”な市場にチャンスがあるのか?
では、なぜ著者のハワード・マークス氏は「市場の効率性には限界がある」と主張するのでしょうか?
その理由のひとつが、「人間の感情」です。
投資家はロボットではありません。
ニュースに一喜一憂し、
欲や恐怖に駆られて非合理な判断をしてしまうことも少なくありません。
感情が市場をゆらす例
- 株価が少し上がっただけで「取り残されたくない」という心理が働き、過熱する
- 一時的な悪材料で「全てが終わった…」と悲観し、パニック売り
こうした反応は、情報が瞬時に広がる現代のSNS時代において特に顕著です。
ネット記事やインフルエンサーの投稿が一気に拡散され、短期的な非効率が生まれるのです。
つまり、市場全体は長期的には効率的であっても、
短期的には人間の感情によってブレが生じる余地があるということです。

短期的に生じる市場の非効率な部分を見つけることが成功する投資家になるための1つの要素。
市場は合理的。でも完璧ではない。
市場が効率的であるという前提は、たしかに安心感を与えてくれます。
しかし、著者は「効率性を盲信しすぎると判断が鈍る」とも警告しています。
- 市場はすべてを織り込んでいるから、考える必要はない
- 上がる時は上がる、下がる時は下がる…流れに任せよう
という“思考停止”は、バブル崩壊や暴落に対して無防備になるリスクがあります。
市場は合理的だが、完璧ではない。
このバランス感覚が、投資家には求められているのです。
探偵パンダの実践:非効率性への備えとリバランス戦略

私は基本的に「市場の効率性」を信じているからこそ、
長期のインデックス積立投資を投資の軸としています。
しかし、完全に効率的だとも思っていません。
たとえば──
- 感情で売られすぎているとき
- 一時的な材料で過剰に反応しているとき
こういった“市場の歪み”を感じたときには、
5%ルール(5%以上下がったらスポット買い)などの戦術を活用しています。
さらに、今後取り入れたいと考えているのが
「ポートフォリオの比率を決めたうえでのリバランス」です。
ポートフォリオ比率=投資家のコンパス
たとえば、

- 株式:60%
- ゴールド:20%
- 現金・債券:20%
といった自分なりの理想比率を定めておけば、
市場の“熱狂”や“悲観”で偏りが生じたときに冷静に調整できます。
- 株が上がりすぎた → 一部利益確定し、他の資産へ分散
- 金が大きく下がった → ポジション追加で再バランス
これにより、安くなったものを買い、高くなったものを売るという
投資の基本を“自動的に”実践できるようになります。
私自身もまだ実践の途中ですが、
今後はこのリバランス戦略も運用の柱にしていきたいと考えています。
まとめ:効率性と非効率性の“瞬間”で戦略を持つ
市場が長期的には効率的であるという前提は、
私たちにとって安心感を与えてくれます。
ですが、市場は常に正しいとは限りません。
- 感情に左右される瞬間
- 一部で過剰反応が起きる局面
- SNS時代特有の短期ショック
こうした“瞬間”にこそ、投資家の判断が問われます。
大事なのは、「すべて市場に任せる」でもなく、
「自分だけが正しい」と思い込むことでもなく、
バランスのとれたスタンスで、市場と向き合うことだと感じています。
次回予告
次回は第3章「バリュー投資を行う」を取り上げます。
“良い会社”を買えば儲かる…と思いきや、それだけでは勝てないのが株式市場の世界。
大切なのは「いくらで買うか?」という視点です。
第3回では、ハワード・マークス氏が重視する「価値と価格の違い」に注目し、
バリュー投資の本質と、あなたの投資スタイルにどう活かせるかを深掘りします。
「高い時に飛びつかず、割安なときに冷静に買える」
そんな判断力を養いたい方は、ぜひお楽しみに!
※当ブログの内容は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
免責事項についてはこちらをご覧ください → [免責事項]





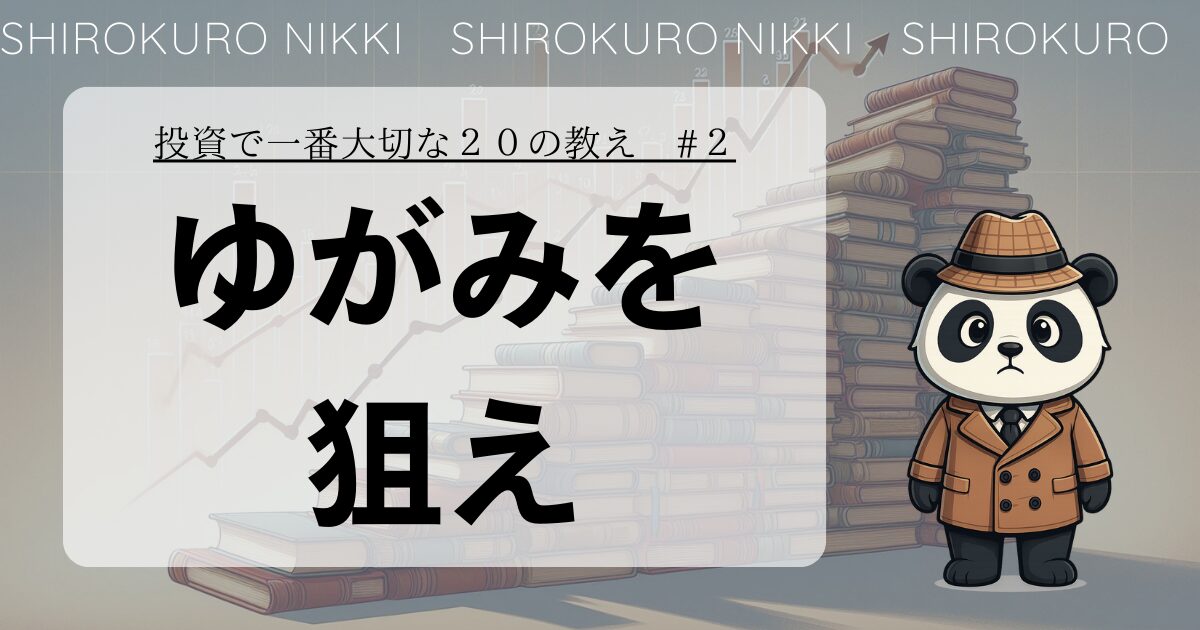
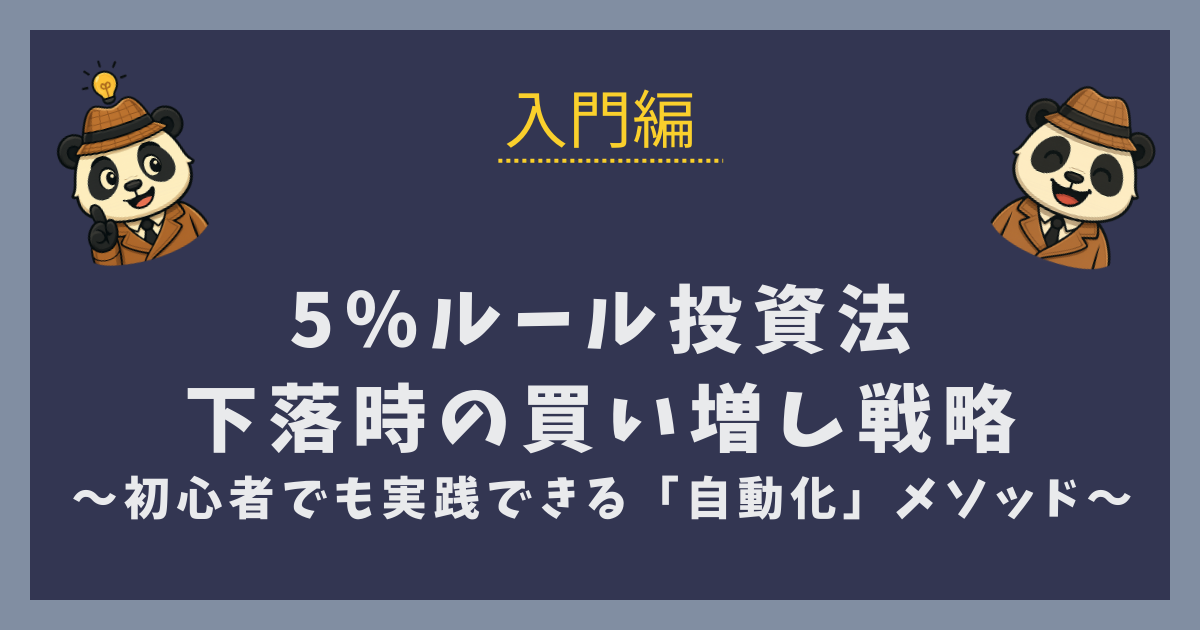


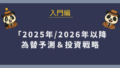
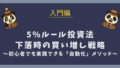
コメント