連載:『投資で一番大切な20の教え』を深く読む
本連載では、ハワード・マークス氏の名著
『投資で一番大切な20の教え』を章ごとに読み解きながら、
私の投資スタイルに照らした実践アイデアを紹介しています。
株式投資における「隠れた常識」を、初心者にも分かりやすくお届けするシリーズです。
「わかってはいたけど、感情が勝ってしまった」
「つい周囲の雰囲気に流されて動いてしまった」
そんな経験は、誰しもあるのではないでしょうか?
今回のテーマは、投資における「心理的バイアス」とその克服法です。
マーケットに潜む罠は、企業業績の悪化や経済政策だけではありません。
最大の敵は――「自分の心」かもしれません。
書籍解説:感情がもたらす“見えないリスク”

● 投資判断を狂わせる心理的要因とは?
ハワード・マークス氏は、次のような人間の心理が投資判断を歪めると述べています:
- 欲望:「もっと儲けたい!」という強欲が冷静な判断を妨げる
- 恐怖:「損をしたくない!」という不安が早すぎる売却を誘う
- 嫉妬・焦り:周りの成功がまぶしく見えて、自分も飛びついてしまう
- 楽観幻想:「これは確実に上がる」という根拠なき期待
- 集団心理:「みんなが買ってるから自分も…」という安心感への依存
投資の世界では、知識不足よりも「感情による誤判断」の方が致命的になりやすいのです。
● 群衆心理に飲まれた結果、市場はバブルや暴落を繰り返す
- ITバブル、リーマンショック、コロナショック…
多くの市場参加者が同じ方向に動くと、相場は極端に傾きます。
極端な強欲(バブル)や極端な恐怖(パニック売り)が積み重なると、
合理性とはかけ離れた価格変動が生まれます。
● 感情をかわすためには「客観視」と「ルール」がカギ
マークス氏が強調するのは、「自分が感情に影響されていないか」を常に自問すること。
- その判断は本当に合理的か?
- 他人の影響を受けていないか?
- ニュースやSNSの雰囲気に引っ張られていないか?
これらを冷静に問い直す力こそ、長期投資家が身につけるべき“メンタル資産”です。
探偵パンダの実践:感情の揺れを「仕組み」で制御する方法
🐼 初心者の方へ:感情で動いてしまうのは“普通”のこと
まず大前提として、感情で動いてしまうのは決して恥ずかしいことではありません。
むしろ、そうなるのが「普通の人間」です。

問題なのは「自分が感情で動いている」と気づかないこと
「なんとなく不安だから売る」
「みんな買ってるし、上がりそうだから自分も」
そんな曖昧な理由で動いてしまうと、冷静な判断はできません。
感情に支配されないための3つの工夫

① 自動化されたルールに従う
私が活用しているのが、
- 積立投資(定額・定期)
- スポット購入のルール
といった、「感情に関係なく動く仕組み」です。
例:ポートフォリオが5%以上下落したら、自動的にスポット買いを行う
→ 「もっと下がりそうで怖い」などの感情が入る余地をなくす
② 情報との距離を調整する
投資系SNSやニュースは貴重な情報源ですが、
見すぎると不安や焦りの原因にもなります。
- 暴落ニュースばかり目にするとパニック売りがしたくなる
- 他人の含み益報告ばかり見て焦りから高値掴みしてしまう
→ 定期的に“情報断ち”をして、自分の投資方針に集中する時間をつくっています。
③ 投資日記で「感情の記録」をつける
私は定期的に、「投資判断時の感情」をメモに残しています。
例:「○○株が急落。怖いけど、分析では割安なので買い増し。冷静でいられた。」
→ 後から読み返すことで、「あの時の感情にどう対処したか」を確認できます。
こうした記録を積み重ねることで、自分の心理パターンを客観視できるようになります。
まとめ
- 投資判断は知識よりも「感情の影響」を受けやすい
- 欲望・恐怖・焦り・嫉妬が合理的判断を歪める
- 仕組み化・ルール・記録を活用して感情に流されない工夫をする
長期で勝ち残るには、「マーケットを読む力」よりも「自分をコントロールする力」が重要です。
次回予告
次回は第7章「逆張りをする」。
群衆が恐怖に震えているときに動けるか?
マーケットの行き過ぎを見抜き、チャンスに変える“逆張り投資”の考え方と実践法を解説します。
※当ブログの内容は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
免責事項についてはこちらをご覧ください → [免責事項]








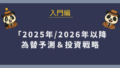
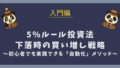
コメント