『探偵パンダの相場推理ノート』とは?
このシリーズでは、日々のマーケットや経済ニュースの中に潜む“違和感”を出発点に、
投資家の視点から「なぜそうなったのか?」「本当の理由は何か?」を考えていきます。
あくまで素人によるひとつの仮説。
それでも、ひとつずつ丁寧に手がかりを拾いながら考えることで、
いつか「相場の真相」に近づけると信じています。一緒に、マーケットの裏側を推理していきましょう。
FRB vs トランプ政権:利下げをめぐる静かな戦争
債券が売られて、株も落ちた。
「これはおかしい」と思ったのが、4月上旬のことだった。
通常、リスクオフ(=市場が不安定になり、リスク資産を手放すような局面)では、国債のような“安全資産”が買われるのが一般的だ。ところが今回は、米国債ですら売られ、10年債利回りは高止まりしたまま。
私の頭に浮かんだのは、「FRBとトランプ政権、実は真っ向からぶつかっているのでは?」という仮説だった。
FRB(米連邦準備制度理事会)は、3月のFOMC(公開市場委員会)で政策金利を据え置いた。CPI(消費者物価指数)は前年比+2.4%まで下がり、目標の+2.0%に近づいているにもかかわらず、パウエル議長は利下げに慎重だ。
「インフレは鈍化してきているが、まだ“持続的な目標達成”とは言えない」
そんなメッセージが読み取れた。
これは中央銀行としては当然の姿勢だろう。早すぎる利下げがインフレ再燃を招くリスクを、誰よりもFRBは知っている。政治的圧力にも屈せず、独立性を保ちつつ、“データ次第”という態度を崩していないのだ。
一方で、選挙を控えたトランプ政権の動きは焦りすら感じさせる。
追加関税の発動──中国への輸入品に最大125%の関税を課し、景気の先行きに強い不安をもたらした。株式市場は大きく動揺し、S&P500は1日で+9.5%の急騰を見せた直後、翌日に-3.4%の急落。
まるで政策実験のような荒れ模様だ。
関税発動の裏には、「株価を一度落としてから国債への資金流入を促し、10年債利回りを下げたい」という思惑があった可能性もある。利回りが下がれば、住宅ローン金利や企業の借入コストも下がる。経済に刺激を与える“金利政策的な効果”を、関税という間接手段で狙ったのかもしれない。
だが、ここで想定外の事態が起こる。
米国債が売られたのだ。
通常なら安全資産として買われるはずの10年債が、今回は“避けられる資産”となった。その結果、利回りは高止まりしたまま。市場では「中国が米国債を売却したのでは?」という観測も浮上した。
考えてみれば当然かもしれない。
財政赤字は過去最大級。36兆ドルを超える米国の債務は、関税による景気減速とセットで、“返済可能性”への疑念を招く。債券市場ですら、ドルへの信認に揺らぎが生じている──そう考えると、株も債券も売られる「異例のダブル安」も納得できる。
その後、トランプ政権は関税を90日間停止すると発表。
投資家のパニックをなだめ、再び株式市場を安定させるための措置だったのだろう。選挙を前に、混乱の責任を問われたくはないはずだ。
私自身は、この混乱にあっても慌てることはなかった。
FANG+は高値圏にあったため、5%ルールに従って静観。GLDM(ゴールドETF)には少しずつ買い増しを入れている。現金比率もある程度維持し、「買わない自由」を確保しておくこともまた、投資家としての戦略の一つだと再確認した。
今はまだ、政策の騒がしさに振り回される局面ではない。
むしろ、こういう時こそ自分のルールを信じ、守ることが未来のリターンにつながる。
FRBと政権。
どちらが正しいかは、あとでしか分からない。
だが、どちらが“信頼できる判断軸”かは、静かに観察していれば見えてくる。
※この記事は、探偵パンダによる“ひとつの仮説”にすぎません。 正解は誰にもわかりません。一緒に「考える」時間を楽しんでいただければ嬉しいです。








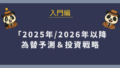
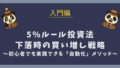
コメント