連載:「インデックス投資は勝者のゲーム」を読み解く
本シリーズでは、ジョン・C・ボーグル氏の名著『インデックス投資は勝者のゲーム』を1章ずつ読み解き、投資初心者〜中級者の方に向けて、エッセンスと実践的な活用法をお届けしています。
ETFは現代の個人投資家にとって欠かせない便利ツール──
しかし、その扱い方を間違えればリターンを損なう「諸刃の剣」にもなりかねません。
第15章では、ETFという投資手段の本質と、それを使いこなすために守るべき「心構え」が説かれています。
書籍の解説

ETFは「投資信託をトレーダーのオモチャにしたもの」?
ボーグル氏は、ETFを投資信託の“進化系”と見るのではなく、
「トレーディング向けに作り替えられた危うい存在」として警戒します。
リアルタイムで売買できることで、つい頻繁に取引してしまい、長期投資の成果を損なう人が多いためです。
「ETFそのもの」は否定していない
ただし、ボーグル氏はETF自体を全否定しているわけではありません。
長期保有を前提とする限り、ETFもインデックスファンドと同様に有効と述べています。
つまり“使い方”こそが問題なのです。
日本市場と新NISAでの広がり
日本でもETFは一般化しており、新NISAの登場により成長投資枠でのETF活用が加速しています。
S&P500や全世界株式など広範な指数に連動するETFは、まさに「正しい使い方」に適した商品と言えるでしょう。
探偵パンダの実践──ETFは「器」のひとつとして活用

私もETFは活用していますが、現在は主にゴールドETF(GLDM)での運用が中心です。
米国株への投資は、基本的には投資信託のeMAXIS Slimシリーズで十分だと考えていますので、ETFには手を出していません。
ETFの最大のメリットは透明性とコストの安さ。
ただし、それに釣られてリアルタイムで頻繁に売買してしまうと、本末転倒。
私はETFであっても「月1回の価格チェック」に留め、買ったら基本的に放置しています。
もし今後ETFをさらに使うなら、証券会社の自動積立機能やポイント投資を活用し、「感情を排除する仕組み」を整えて使いたいと考えています。
ETFは「魔法の道具」ではなく、あくまでインデックス投資の器の一つ。
この認識を持つだけで、使い方は大きく変わります。
初心者へのアドバイス
- ETFの中身を理解する
VOO(S&P500)やVT(全世界)など王道ETFを選びましょう。テーマ型やレバレッジ型は長期投資には不向きです。 - 売買は最小限に
ETFは取引のしやすさが魅力ですが、それゆえ“売買したくなる”リスクも。投資信託と同じ感覚で「買ったら持ちっぱなし」を徹底しましょう。 - コスト構造に注意
ETFは購入時に手数料がかかる場合も。特に外国ETFの場合は為替手数料も発生するため、トータルコストで比較を。 - ETFの「型」に縛られすぎない
ETFは手段です。内容・運用方針・コストのバランスを見極め、自分の資産形成戦略に合うものを選びましょう。
まとめ
ETFは「使い方次第」。
長期投資家が中身を理解し、売買衝動を抑えて運用すれば、強力な味方になります。
しかし、短期的な値動きや流行に流されれば、投資効率を大きく損なうことにもなりかねません。
本章のメッセージは明快です──ETFは優れたツールだが、ツールに支配されるな。
次回予告
次回は【連載⑮】第16章「インデックスファンドが市場に勝つことを保証する」に進みます。市場平均を得るだけで“勝てる”理由とは? その数学的な根拠と精神的優位性を解説します。どうぞお楽しみに。
※当ブログの内容は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
免責事項についてはこちらをご覧ください → [免責事項]







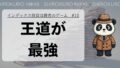
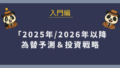
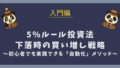
コメント