連載:『投資で一番大切な20の教え』を深く読む
本記事は、ハワード・マークス氏の名著『投資で一番大切な20の教え』を20章にわたって解説する連載の第3回です。(3章、4章)
今回は投資判断の根幹となる「本質的価値(intrinsic value)」の考え方と、それを見極める力の重要性について深掘りしていきます。
なぜ「価値」が出発点なのか?
本書の第3章でマークス氏は、
「何を買うかよりも、いくらで買うかが重要だ」
と語ります。
いくら優れた企業であっても、それを割高な価格で買ってしまえば、
長期的なリターンは期待できません。
逆に、市場で一時的に過小評価されている資産を見つけて購入できれば、
大きなリターンが期待できます。
つまり、投資における出発点は「この資産の本質的価値はいくらか?」を考えることなのです。
価値と価格はいつも一致するわけではない
実際の市場では、「価値」と「価格」はしばしば乖離します。
例①:2009年 リーマンショック後の米国株
当時の混乱で多くの優良企業がパニック売りされ、価値より大きく安い価格で放置されていました。
ウォーレン・バフェットはこの局面で、「米国株は割安だ」として積極的に投資を行っています。
例②:2021年 ゲームストップ株騒動
SNSによる熱狂で個人投資家が集中した結果、
企業価値に見合わない高値となりました。
最終的には価値との乖離の反動で株価は急落しています。
このように、「割安な価格で価値あるものを買う」という姿勢こそが、バリュー投資の本質なのです。
2024〜2025年の今、「バリュー」は再び脚光を浴びている
近年では、金利上昇やインフレ懸念を背景に、グロース株の過熱が沈静化し、
バリュー株・高配当株への再評価が進んでいます。
たとえば:
- 米国のエネルギー株や金融株は、2022年以降に一時的な低評価を受けた後、業績改善とともに見直されました。
- 日本株も長期低迷を経て、2023年に企業改革を背景にバブル後の最高値を更新。
現在でも「価値を見極めて割安なうちに投資する」という原則は有効であり、むしろ不透明な相場だからこそ輝く指針です。
探偵パンダの実践:長期投資家が「価値」を活かす方法

1. 積立中のETFや投信の評価を時々確認
定期買付をしている資産のPERやPBRが歴史的に見て高い水準かどうかを
年1回程度確認してみましょう。割高なら追加投資の金額を調整するのも選択肢です。
2. スポット買いは「価値との乖離」をヒントに
相場が下落したとき、本質価値が傷んでいない資産が売られていないかを探します。
私が実践している「5%ルール」も、そうしたチャンスを活かすものです。
3. ゴールド投資にも価値の視点を
例えば、インフレ率や実質金利と比較して「今の金価格は高すぎるか?割安か?」
という視点を持つと、安定資産でも割高買いを避けることができます。
行動プラン – 価値を見る習慣を育てよう
- 企業価値を学ぶ:
売上、利益、資産といった決算の基本を確認。
「この企業の株価は割高?割安?」を自分で考えてみる。 - 「割安候補」リストを作る:
気になる企業やETFをウォッチしておき、「この価格なら買いたい」という目安を決めておく。 - インデックスの構成比率をチェック:
世界株インデックスなどでも、国・セクターごとの比率が偏っていないか確認。
気になる場合はリバランスを検討。
まとめ

次回予告
次回の第4回では、「リスクとは何か?」に迫ります。
投資における「リスク」は本当に“値動きの幅”だけなのか?
資産を守りながら増やすための「リスクとの付き合い方」を深く解説していきます。
※当ブログの内容は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
免責事項についてはこちらをご覧ください → [免責事項]







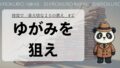

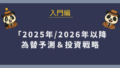
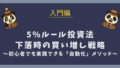
コメント