連載:「インデックス投資は勝者のゲーム」を読み解く
資産運用の成否を左右する最重要テーマ、それが「アセットアロケーション(資産配分)」です。
本記事では『インデックス投資は勝者のゲーム』の第18章と第19章を一体として読み解き、株式と債券の割合をどう設計し、引退後にどのような運用戦略を取るべきかを考察します。
人生100年時代の投資家にとって、今日の判断が将来の安心につながります。
書籍解説

第18章:アセットアロケーション(その1)株と債券
この章では資産配分の基本として、株式と債券の比率について解説されます。
ベンジャミン・グレアムは「株50:債券50」を基準とし、リスク許容度に応じて25:75~75:25までの調整を提唱しました。
一方、ボーグル氏は若年層には株式80%:債券20%という攻めの構成を勧めています。
資産配分の決定には「リスクを取る能力(収入や年齢)と意欲(変動への精神的耐性)」の2軸を意識することが重要です。
また、リバランスについても議論されており、配分を守るための定期調整が合理的行動を促す一方で、好調資産を伸ばす機会を削ぐというトレードオフもあると述べられています。
第19章:アセットアロケーション(その2)引退後の投資とバランスファンド
引退後の運用では「元本維持」が優先され、株式よりも債券比率を高めるのが一般的です。
年金は“債券的資産”と見なすことができ、将来受け取る年金額を換算することで現在の資産配分に活かすことも可能。
また、4%ルール(年間4%ずつ取り崩す)を目安とした資産管理や、
自動で資産配分を調整してくれるバランスファンド・ターゲットデートファンドの活用についても触れられています。
これは、老後の手間を減らしつつ資産を保全するための有効な手段として紹介されています。
探偵パンダの実践

私は20代であり、現在の株式比率は約90%です。年金という“見えない債券”の存在を考慮すれば、現役時代に株式比率を高めに持つことに納得がいきます。
国際分散については、ボーグル氏は米国株中心でも十分と述べています。
一方私はS&P500に加え、他国のへも分散しています。米国市場の優位性を信じつつ、非米国市場の成長可能性も取り込みたいという考えです。
なお債券ファンドは現在保有していませんが、将来的には資産保全フェーズに入ったタイミングで比率を引き上げていく予定です。バランスファンドも現状では考えていません。
リバランスについては、原則として入金調整で対応し、極端な乖離があればスポット売買を検討する方針です。目標とする配分を厳格に保つというより、ゆるやかな再調整で大きな偏りを避けるスタイルを取っています。(多くても年に1回程度)
まとめ
資産配分は一人ひとりの状況と価値観によって最適解が異なります。
若いほど株式比率を高めに、引退が近づけば債券比率を高めにというのが基本ですが、
「年金=債券」と見なすことで、より柔軟な戦略が可能です。
また、4%ルールを一つの目安としつつ、暴落時には取り崩しを減らすなど、
柔軟な対応が資産寿命を伸ばすカギとなります。
要は「自分の戦略を明確に持ち、それに沿って一貫性を保つ」ことが成功の秘訣です。
次回予告
次回はいよいよ最終章、第20章「インデックス投資を続けることの価値」について取り上げます。長期投資の果てに何が待っているのか──ボーグル氏が読者に遺したメッセージを探偵パンダと一緒に読み解いていきましょう。
※当ブログの内容は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
免責事項についてはこちらをご覧ください → [免責事項]





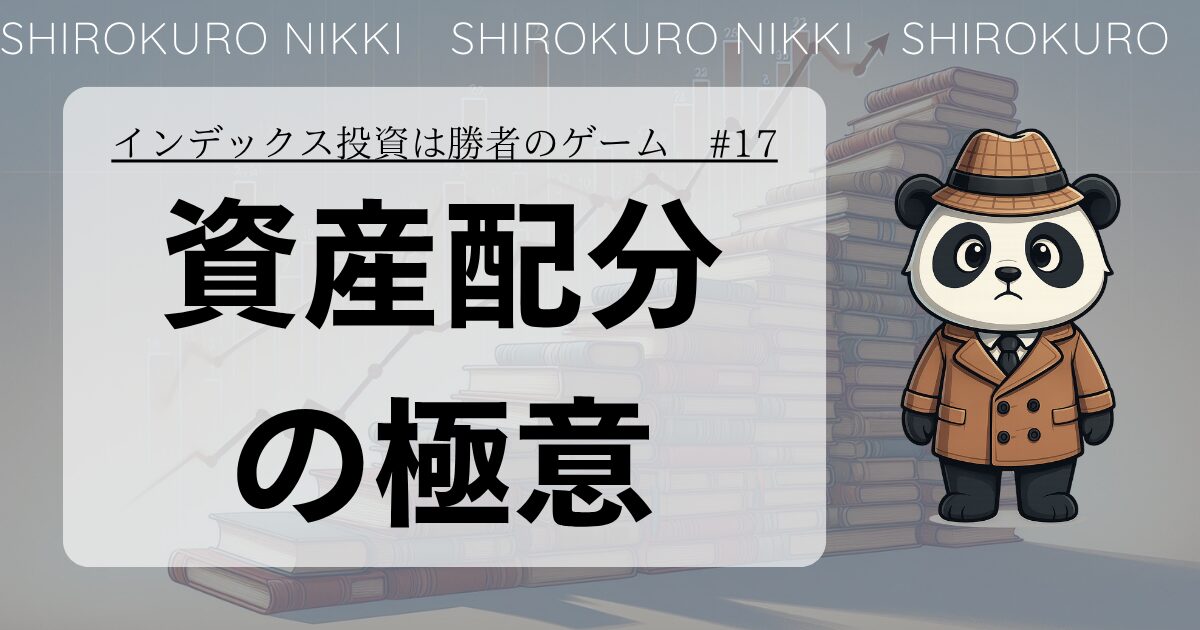
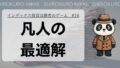
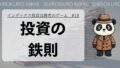
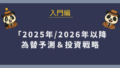
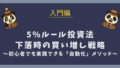
コメント