「安全資産」だったはずの米国債が売られた理由
債券は安全資産──そんな常識が覆ったのは、つい先日のことだった。
株価が急落する中、投資家たちは通常なら国債へと資金を逃がす。しかし今回の市場では、株とともに債券までもが売られた。米国10年債の利回りは高止まりし、市場は「なぜ安全資産が買われないのか?」という違和感でざわめいた。
私はこの異変を、「ただの金利変動」として見過ごすわけにはいかなかった。
この動きの背景にある仮説のひとつ──それが中国による米国債の売却だ。
確かに、中国が米国債を保有しているのは、経済安定のためであり、戦略的な金融手段でもある。だが近年、中国と米国の覇権争いは激化。中国は将来的にドル基軸の時代を終わらせたいと考えているはずだ。
そのための第一歩として、「ドルの信用を揺るがせる」という選択肢は合理的だろう。
実際、中国は金の買い増しやビットコイン保有へのシフトなど、ドル以外の資産への投資を拡大している。ロシア・ウクライナ戦争における米国の制裁措置──ドル決済からの排除──を見れば、中国が同じリスクを警戒するのは自然なことだ。
米国債を売却することで、ドルの金利を押し上げ、米国経済にプレッシャーをかける。これは「通貨戦争」のひとつの形といえる。
だが、売り手は中国だけとは限らない。
日本もまた、米国債の最大保有国として注目されている。ここ最近の円高・ドル安の流れを見れば、日本が為替リスクを回避するために米国債を売却していても不思議ではない。
さらに、米国の政治リスクや財政赤字への懸念から、機関投資家たちが「米国の信頼性」に疑問を持ち始めている可能性もある。トランプ政権による関税政策や連邦債務の拡大が続けば、米国債を“絶対的な安全資産”とみなすのは、もはや過去の話かもしれない。
私は、こう考える──
短期的には、米国債は依然として安全資産として機能するだろう。しかし、長期的に見ればその神話は揺らぎ始めている。
国家には栄枯盛衰のサイクルがある。ローマ帝国も、スペイン帝国も、そしてイギリスも──かつて世界を制した国々は、いずれも衰退の道を辿った。
アメリカも例外ではない。基軸通貨ドルの地位が、未来永劫に続く保証はどこにもない。
そう考えたとき、私は「次の安全資産」を探し始める。
金は長年その役割を果たしてきた。そして今、もうひとつの可能性──ビットコインという存在が現れた。
直近ではその価格が乱高下し、「安全資産としての役割は果たせていない」という声も多い。だがそれは、通貨の歴史の中では“幼少期の揺らぎ”に過ぎないのかもしれない。
技術的な分散性、国家からの独立性、そしてグローバルな受容性。これらが今後、金とは異なる形での「信頼」を生む可能性は、決してゼロではない。
私のポートフォリオでは、GLDM(ゴールドETF)への比重をやや高め、同時に仮想通貨市場の動向もウォッチしている。
まだ「全面的な代替」とまでは考えていない。だが、リスクが増す時代において、**“信頼の分散”**こそが本当の意味での資産防衛だと思っている。
今回の債券売りは、単なる金利の話ではない。 それは、「信頼の構造」に小さなヒビが入った瞬間なのかもしれない──。
※この記事は、探偵パンダによる“ひとつの仮説”にすぎません。 正解は誰にもわかりません。一緒に「考える」時間を楽しんでいただければ嬉しいです。








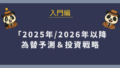
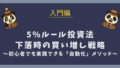
コメント