この記事は、オークツリー・キャピタルの共同創業者である ハワード・マークス氏へのインタビュー動画 をもとに作成しました。動画内で語られた市場観や警告を整理し、私自身の解釈や意見を加えてまとめています。投資家にとって今後の判断材料になれば幸いです。
ハワード・マークスの見解

オークツリー・キャピタルの共同創業者、ハワード・マークス氏は「株式はファンダメンタルズから見て割高」であり、「バブルの初期段階に突入している可能性が高い」と語りました。
その背景には、2008年のリーマンショック以降16年にわたり大きな市場調整が起きていない点があります。コロナショックのような一時的な下落はあったものの、持続的ではなく、投資家は「楽観的」に市場を見がちになっているのです。
彼は「投資家が犯す最大の間違いは、今の状態が永遠に続くと考えること」だと指摘。
実際には平均回帰が必ず起こり、過去の過熱はやがて冷却へと転じる可能性が高いと強調しました。
「人々は株を『好き』から『すごく好き』『大好き』『好きすぎる』へと進み、その延長線上でバブルが生まれる」
── ハワード・マークス
現在のS&P500の評価

S&P500の過去2年間のトータルリターンは58%に達し、その半分以上が「マグニフィセント・セブン(Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、NVIDIA、Tesla)」によるものでした。これらの企業は素晴らしい業績と収益力を持ち、時価総額で指数全体の3分の1を占めています。
株価収益率(PER)は平均33倍と高水準ですが、過去の「ニフティ・フィフティ」がPER60~90倍で取引されていたことを考えると「必ずしも不合理ではない」とマークス氏は述べます。
むしろ問題は、残りの493社のPERが平均22倍に達しており、S&P500全体が歴史的に見ても割高になっている点にあると指摘しました。
さらに、関税やインフレ懸念、財政赤字の拡大は市場のリスク要因であり、投資家の楽観を支えてきた土台を揺るがす可能性があります。
投資家が意識すべきこと
マークス氏は「今すぐに調整が起こるわけではない」としつつも、防御的姿勢を強めるべきだと示唆しました。自身の専門である債券投資を引き合いに出し、株式から一部シフトするのが妥当だと語っています。
また、投資家が心に留めるべきは以下の2点です。
- AIなど新技術は確かに世界を変える可能性があるが、すべての企業が勝者になるわけではない。
- 相場の過大評価は証明できないが、いずれ「上昇から懸念」へと移行する。
そして具体的な投資行動の参考として、以下の INVESTCON(投資行動指針) を紹介します。
- 6. 購入をやめる
- 5. 積極的な保有を減らし、防御的な保有を増やす
- 4. 残りの積極的な保有株を売却する
- 3. 防御的な保有物も削減する
- 2. すべての保有物を排除する
- 1. ショートに転じる
※ただし、INVESTCONの下位ステップ(3・2・1)を実行する確実性を合理的に持つことは不可能。現時点では「5(積極的な株式比率を減らし、防御的資産を増やす)」が妥当な段階と考えられます。
個人的な意見・考察

マークス氏が「493銘柄の割高さ」を強調した点は興味深いです。確かにマグニフィセント7は収益力や市場規模を考えれば、その評価は一概に割高とは言えないでしょう。むしろ、それらを含む投資信託に投資することは合理的かもしれません。
一方で、マークス氏は債券を安全資産として推奨していましたが、これは自身の立場(債券を販売する側)からの「ポジショントーク」の可能性も否めません。私は現時点で債券購入は考えていません。その代わり、米国以外の国や金などへの分散投資によって防御を図りたいと考えています。
また、彼の著書『投資で一番大切な20の教え』にもあるように、相場は振り子のように「強気」と「弱気」を行き来します。平均回帰とは「平均値にピタリと収束する」という意味ではなく、過大評価や過小評価といった極端な状態から、平均的な水準へ戻ろうとする力学的な動きを指します。振り子が永遠に片側に動き続けることはなく、いずれ必ず反転するのです。
投資家はこの事実を頭に入れ、強欲や楽観が支配する局面では特に警戒を怠ってはならないと改めて感じました。
書籍紹介
ハワード・マークス氏の著書 『投資で一番大切な20の教え』 は、投資家にとって必読の名著です。長年の経験を通じて学んだ「リスク管理」「市場心理」「平均回帰」などの本質的な考え方が、分かりやすくまとめられています。特に「市場は振り子のように行き過ぎては戻る」という洞察は、今回のインタビュー内容とも強く結びついています。
投資の判断に迷うとき、相場の過熱に不安を感じるときに読み返すことで、冷静さを取り戻すきっかけになる一冊です。
※当ブログの内容は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
免責事項についてはこちらをご覧ください → [免責事項]





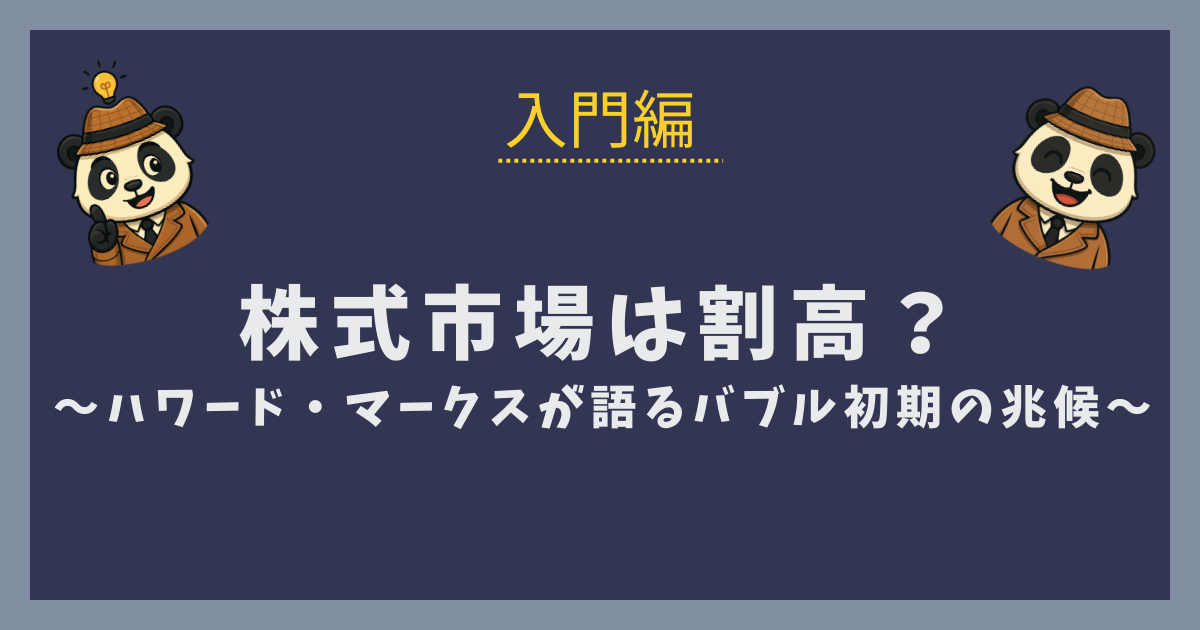
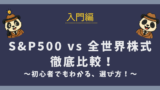
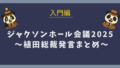

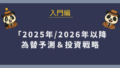
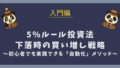
コメント