2025年5月、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイの年次株主総会が開催されました。
世界中の投資家が注目するこの総会には、株価や経済政策だけでなく、バフェット氏の哲学や価値観に触れる場としての重みがあります。
本記事では、株主総会で語られた通貨リスク・日本株投資・貿易政策・アメリカ経済の行方などの発言を取り上げつつ、
投資初心者~中級者でも理解できるように、丁寧に解説と考察を加えています。
そして何より、94歳となったバフェット氏が今なお語るその姿勢に、
投資家としてだけでなく一人の人生の先輩としての学びがあると感じました。
現金3,350億ドルの真意──「投資しない勇気」と時間感覚の美学
要点
バフェットは「魅力的な投資先が見つからない今は、現金を持って待つべき時期」と明言。フルインベストメントを避け、将来の好機に備えている。
質問内容
「現在、バークシャーは現金および短期投資で3,000億ドル以上を保有しており、これは総資産の約27%に相当します。
これは過去25年間の平均13%と比べて歴史的に高い水準です。また、バークシャーは米国債市場全体の約5%を実質的に保有するに至っています。
保険債務の流動性確保に加え、この現金保有は市場価格の高騰に対するリスク回避策なのでしょうか?
あるいは、経営陣の交代に際して、グレッグ・エイベル氏に柔軟な資本配分を可能にするための戦略的準備なのでしょうか?
そして、近い将来に魅力的な提案が舞い込むことを期待しているのですか?」
バフェットの回答(翻訳)
「私たちにとって納得のいく、理解しやすい、価値があり、損失を心配しなくてよいものがあれば、1,000億ドルでも投資するでしょう。
投資の問題は、物事が計画的・秩序的には起きないことにあります。私は約1万6,000日、市場に関わってきました。
しかし、毎日素晴らしいチャンスが来るわけではありません。チャーリー・マンガーはよく『お前はやりすぎだ。人生で本当に素晴らしい投資は5つあればいい。50やるよりよほど成功する』と言っていました。
💬【現金の規模について】
「私たちは今、3,350億ドルの現金と短期米国債を保有しています。
正直なところ、本当は500億ドルくらいで済む環境が理想的です。
けれど、現実はそううまくいきません。常にフルインベストメントを目指さないことで、我々は大きな利益を上げてきました。
インデックス投資家のように市場に居座り続けるやり方を否定するつもりはありません。
でも、我々は“そのビジネスをやる”と決めたのです。だから、不規則に動くことで優位を取りに行く戦略を取っています。」
💬【チャンスの到来と準備】
「物事は、時に、驚くほど魅力的に見える瞬間がやってきます。
長期的なトレンドは上向きだとしても、その瞬間が“明日”なのか、“5年後”なのかは誰にもわかりません。私にも、グレッグにも、アジットにもわからない。
にもかかわらず、人はそうした話ばかりしてしまうのです。でも私は確信しています──
『ごく稀にですが、またいつか、いつになるかは分かりません。来週かもしれないし、5年後かもしれないし、50年後ではないでしょうが、お金があってよかったと思えるような品々が、次々に現れるのことを。』
解釈:バフェットが語る「準備の思想」
この発言ににじむのは、「待つことは行動である」という逆説的な真実です。
パッシブではなく、機動性あるアクティブの模範
“常にフルインベストメント”という現代の投資の常識に真っ向から立ち向かう姿勢。機会を待ち、集中して投資する姿は、まさに「少数精鋭の打席」に賭けるバフェットらしい合理性です。
現金=消極ではなく、能動的な戦略
利回りを生まない資産をこれだけ大量に保有することを「非効率」と考えるのは、短期的な視点です。バフェットは、今は好機ではないという判断を明確にしているのです。
未来を予測せず、来た時に備えるという投資哲学
「明日ではないが、50年後でもない」。この時間軸の捉え方が、長期投資家に必要な視座だと思います。来るかどうか分からない未来に、ではなく、必ず来る未来の“タイミング”に備えている。
探偵パンダの実践と迷い:構えて待つか、居続けるか
私自身、スポット購入の5%ルールを採用しながらも、基本はインデックス積立で市場に居続けるという形を取っています。
今回のバフェットの発言を聞いて改めて感じたのは、「投資とは“待つこと”も含めて行動である」ということです。
ただし、私たち個人投資家の場合は、
- そもそも投資対象を自分で探し出す時間が限られている
- 割安かどうかを見極める目もまだ鍛錬中である
という現実もあり、市場に居続ける(フルインベストメント)という戦略も十分合理的だと思います。
とはいえ、下落時に備えて一定の余力を持つ“待機資金”があることで、
- 焦って売らない
- チャンスを掴める
という行動の自由度が増すのも確か。

「どちらが正しいか」ではなく、「どちらの姿勢を自分が無理なく続けられるか」
それこそが、長期投資において一番大切な判断軸なのかもしれません。
日本株を“50年保有する”という覚悟─商社投資に込められた信頼と哲学
要点
バフェットは日本の5大総合商社を「50年、あるいは永遠に保有する」と語り、日本経済・企業文化への信頼を明確に示した。
🗨️ 質問(翻訳)
「日本の消費者物価指数(CPI)は直近で3%を超え、目標の2%に近づいています。
FRB、ECBなどが利下げを検討する中、日本銀行は利上げへの強い意欲を示しています。
日銀の利上げは妥当だと思いますか?また、それはバークシャーによる日本株投資や、現在の利益の実現に影響を与えるでしょうか?」
バフェットの回答(翻訳)
「経済面での最善の行動は、日本国民に決めてもらいます。それが素晴らしい点なのです。
日本への投資を始めて約6年が経ちました。
当時、小さな日本企業ハンドブック(四季報)を読んでいたところ、5社の総合商社が極めて割安で売られていることに気づいたのです。約1年をかけてこれらの株式を取得し、その過程で各社の人々と関係を築きました。
私とグレッグが実際に見聞きしたものはすべて、時間が経つほどに好印象へと変わっていきました。」
💬【対象企業への出資比率】
当初、出資比率10%の上限を設定し、それを超えることはしないと明言していましたが、
現在その水準にかなり近づいており、上限の緩和について協議中です。グレッグの意見も代弁しますが──今後50年間、これらのポジションを売却することは考えていません。」
解釈:利上げにも動じない“企業を見る目”
この発言から見えてくるのは、金利政策や為替動向の変化に一喜一憂せず、企業そのものの価値にフォーカスしている姿勢です。
- 利上げは投資判断に影響しない
バフェットはあくまで「企業の本質的な価値」を基準にしており、金融政策の短期的な変動には左右されていません。 - 日本の商社に対する構造的な信頼
“50年保有する”という言葉は、価格の上下ではなく、経営と資本配分の優秀さ・文化との相性・安定したビジネスモデルへの信頼に基づいています。 - 文化的な相性まで重視
バフェットは単なる数値評価だけでなく、「関係性・信頼・文化の一致」を長期投資の条件に入れていのではないでしょうか。
探偵パンダの実践と視点:この投資姿勢は個人でも応用できるか?
私自身、日経平均連動の投資信託(eMAXIS Slim 国内株式)を少額積み立てる中で、日本株をどう評価するかは悩みの種のひとつでした。
特に日本は長年デフレ傾向にあり、「経済成長を信じづらい」というイメージもあって、つい後回しにしてしまいがちです。
ただ、今回のバフェットの発言を受けて強く感じたのは、
「個人投資家にとっても、日本株を『安定成長・分散・収益性』の観点から再評価する価値はある」
ということです。
もちろん、私たちが商社株を大量取得するのは現実的ではありませんが──
- 配当利回りが高い
- 海外事業や資源価格に強い
- 国内外で安定需要がある
という特徴を持つ商社株や、高配当株ETFなどを長期保有する戦略は、バフェットの哲学に通じるところがあります。
🧩 バフェットが語る「文化的相性」の意味とは?
「ジョージアコーヒーが日本でコカ・コーラ最大の商品になっている」
「iPhoneやアメックスが日本で米国外トップの売上を誇る」
この発言は、一見すると単なる売上自慢にも聞こえますが、バフェットが本当に伝えたかったのは、次のようなメッセージではないでしょうか。
日本経済と消費市場への静かな信頼
- 「アメリカの製品が売れる=日本には購買力がある」
iPhoneやアメックス、ジョージアコーヒーなどが売れている背景には、日本国内の安定した消費市場と経済基盤があることを示唆しています。 - バフェットはよく「買いたい企業がある国」に投資すると言いますが、それはその国の経済・法制度・消費環境が信頼できるということの裏返しです。
- 今回のように具体的な売上実績を挙げるのは、「だからこそ日本は投資対象として優れている」というメッセージでもあります。
文化の違いを尊重し、共存できる関係性
「私はチェリーコーク派だけど、彼らは私をジョージアに変えようとはしない。
私も彼らを変えようとはしない──それが完璧な関係だ。」
この言葉に込められているのは、次のような思想です:
- 無理に融合するのではなく、相手の文化・好み・やり方を尊重したうえで共に成長することが、真のパートナーシップであるという考え。
- 投資は「資金を投じる」だけでなく、「相手を尊重し、信頼する」ことでもある。
- 数値だけで選ぶのではなく、“一緒に長く働きたい相手かどうか”を重視する──これはビジネスでも人生でも共通する感覚ではないでしょうか。
このように、バフェットの発言には、日本という国の底堅さへの評価と、文化的相性を含めた“長期投資の条件”が込められています。
投資判断をするとき、「割安かどうか」「リターンが高いか」だけでなく、
「この企業と10年後も付き合っていたいか?」
と自分に問いかけてみるのも、良い判断基準になるのかもしれません。
通貨の信認と貿易摩擦─バフェットが恐れる見えないインフレ
要点
バフェットは「政府は通貨の価値を下げたがる本能を持つ」と語り、米国の財政政策に対して明確な危機感を示した。
🗨️ 質問(翻訳)
「2025年には米ドルが他の外貨に対して急速に下落する兆候が見られます。バークシャーは為替リスクと、それが四半期や年間の収益に与える影響を最小化するための対策を講じているのでしょうか?
また、バークシャーは現在、為替リスクと日本株投資を相殺するために日本円での借入を行っていますが、今後、外貨建て資産へのヘッジなしの投資を検討していますか?」
バフェットの回答(翻訳)
「はい、私たちは常に一定の対策を講じてきました。ただし、今回の日本円建て借入は、これまでとは異なる特別なケースです。
日本株に関しては非常に長期的な視野で保有するつもりであり、資金調達コストが非常に安いため、円建ての調達を部分的に組み合わせました。
ただし、これはバークシャーの通常の方針ではなく、初めての試みです。これまでも私たちは外貨建て資産を多く保有してきましたが、それによって四半期ごとの利益を操作しようとしたことは一度もありません。
重要なのは、“今月の為替変動”ではなく、**“5年後・10年後にどうなっているか”**です。」
💬【ドルへの懸念と通貨の本質】
「当然ながら、我々が保有したくないのは“地獄に向かう通貨”です。
米ドルに関して、私たちが最も懸念しているのはまさにこの点です。政府には、自国通貨の価値を時間とともに下げたいという本能的な傾向がある。
独裁者であろうと民主国家の代表者であろうと、この傾向は変わりません。米国において私が最も恐れているのは“財政政策”です。
現在の制度やインセンティブは、通貨にとって悪影響を与える方向に向かっています。これはアメリカに限った話ではありません。
世界中で通貨が制御不能に陥るのを、私は何度も見てきました。“呼吸するように通貨を切り下げる国”もあるのです。」
💬【過去の通貨取引と“警戒”の姿勢】
世界は常に変化しています──だから私のこの発言を“予測”とは受け取らないでください。」
「私たちが過去に行った通貨取引は1回だけです。
それは12カ国の通貨へのロングポジション(=ドルのショート)でした。
大きなリスクを取りましたが、数十億ドルの利益を得ました。ただしそれ以降は繰り返していません。
ですが今後、もしアメリカで大きなインフレ的失敗が起これば、
他国通貨に資産を避難させる必要が出てくるかもしれません。
解釈:通貨の信認は“見えないリスク”
このやり取りからは、バフェットが「為替リスク」を短期的な変動よりも、“通貨の信頼そのもの”の崩壊リスクとして捉えていることが明確に伝わってきます。
- 「通貨は本質的に価値を下げる運命にある」
通貨を発行するのは人間であり、政府であり、彼らは選挙や景気対策という都合を優先する。つまり、“時間が経てば通貨の価値は下がる”のが自然な構造なのです。 - 財政政策がドルの最大リスク
米国はかつて“世界の基軸通貨”として無条件の信頼を集めてきましたが、
近年は財政赤字の拡大、利下げ圧力、巨額の債務など、ドルの価値を揺るがす材料が山積みです。 - インフレは「国の信頼」を静かにむしばむ
過去にも多くの国が、インフレや通貨危機によって国民の資産を事実上“奪ってきた”歴史があります。
バフェットはそうしたリスクを「見えないうちに進行するもの」として、静かに警鐘を鳴らしているのです。
探偵パンダの実践と視点:インデックス投資家は通貨にも分散すべき?
私自身、主に円建てで積み立て投資をしてきましたが、近年の円安や米国の財政不安を見ていると、

「本当に“日本円だけ”で大丈夫だろうか?」
という不安がよぎることがあります。
今回のバフェットの発言を受けて強く感じたのは、

通貨リスクは“目に見えないが確実に存在する”ということ。
実践的なアクションとして考えていること:
- 外貨建て資産(例:ドル建てETF)をポートフォリオに一部組み込む
- インフレ耐性のある資産(例:金ETFや一部の実物資産)への分散
- 通貨分散の観点で「グローバル分散投資」を再評価する
また、将来的には「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」のようなドル建て債券ETFの購入を検討しています。
補足解釈:なぜバフェットは“円建て”で日本株を買ったのか?
バフェットは、バークシャーが日本の商社株を購入する際、円建てで資金を調達し、円建てで株式を購入したと述べました。
この背景には、以下のような明確な理由があります。
為替リスクを構造的に抑えるため
- 米ドルを円に替えて日本株を買うと、「株価×為替レート」の二重リスクが生じます。
- しかし「円を借りて、円で株を買う」なら、為替変動は損益に直接影響しません。
- これはいわば、“投資と調達の通貨を一致させてリスクを抑える”手法です。
日本は超低金利だから、借入コストが非常に安い
- 日本では長年ゼロ金利政策が続いており、調達コスト(利子)を大きく抑えられる。
- これはバークシャーのような大企業にとって、非常に効率の良い資金調達手段となります。
- バフェット流の“ローリスク・ローコスト投資”の一環といえるでしょう。
短期の為替ではなく、5年後・10年後を見ている
バフェットはこう述べています:
「今月の為替レートではなく、5年後・10年後にどうなっているかが重要だ。」
これは、「為替を予測するのではなく、為替のブレに振り回されない投資構造を作るべき」というメッセージです。
つまり、ドルが円に対して高いか安いかではなく、
- 為替を考えなくて済む状態を作る
- 企業価値の成長に集中する
という、“予測しない代わりに備える”バフェットらしい合理性が背景にあるのはないでしょうか。
通貨の価値は“じわじわ失われる”
バフェットの言葉にはこんな警告が含まれていると、私は受け取りました。
「株価の暴落はすぐ分かる。けれど、通貨の価値が下がっていく過程は見えにくい。」
私たち個人投資家ができるのは、少しでも視野を広げて、
「資産が増えること」だけでなく「減らさないこと」にも目を向けることではないでしょうか。
貿易は武器ではない──関税に対するバフェットの一貫した懸念
要点
バフェットは「貿易を経済戦争の道具にしてはならない」と繰り返し主張し、相互利益と共存の視点から関税に否定的な立場を取った。
🗨️ 質問(翻訳)
「2003年のフォーチュン誌の記事では、あなたは貿易赤字を抑えるために輸入証明書が必要だと主張し、これらの輸入証明書は実質的に関税に相当すると述べました。
しかし最近では、関税を経済戦争行為と呼んでいます。
貿易障壁に対するあなたの見方は変わったのでしょうか?それとも、輸入証明書は関税とは異なるとお考えですか?」
バフェットの回答(翻訳)
「貿易は経済戦争の手段になり得ることは確かです。
そして、実際にそうした対応によって、アメリカに悪影響を及ぼしてきたとも考えています。私たちは世界の他の国々と貿易すべきです。
我々は自分たちの得意分野を活かし、他国も同様にすべきです。現在、8カ国が核兵器を保有しており、中には非常に不安定な国もあります。
そんな中で「我々は勝者だ」と一方的に主張する世界の構築は、決して良い考えではありません。重要なのは──貿易を武器にしてはならないということです。」
💬【歴史観とグローバル共存へのメッセージ】
「アメリカは250年前、ほぼ“無”の状態から、世界有数の国家へと成長しました。
私たちの成功は誇るべきものですが──世界の75億人から好かれていない中で、3億人だけが自画自賛している状況は、傲慢であり間違いです。
他国が豊かになることは、我々が貧しくなることを意味しません。
むしろ、共に豊かになり、安全性も高まるのです。
それが、真に合理的な世界の姿だと思います。」
解釈:バフェットの「貿易観」は、長期投資と同じ哲学
1. 貿易は「ゼロサム」ではなく「プラスサム」
- 他国が豊かになっても、自国が損をするわけではない
- 「他者の成功=自分の失敗」と捉える発想自体が誤っているという視点
これは投資の世界で言えば、「他人が儲けている銘柄に嫉妬して自分の軸を失うな」という教訓にも通じます。
2. 貿易障壁は短期的な政治策、だが長期的には信頼を損なう
- 関税などの制裁的政策は、一時的には自国産業を守るように見える
- しかし、長期的には“信頼のネットワーク”を破壊する
バフェットは、一貫して“敵を作らない”戦略を好む人物です。それは投資でも外交でも同じです。
3. 「武器ではなく、橋をかける」姿勢
バフェットは「貿易を武器にしてはならない」と繰り返し述べていますが、それは政治的スタンスではなく、経済合理性に基づく発言です。
- 無理な競争をするより、得意分野を活かし合う方が全体として豊かになる
- 投資も同じ──誰かを出し抜くより、自分の強みを最大化する
という、経済と投資をつなぐ“共通原理”のようなものを語っているように感じます。
貿易も投資も、“敵を作らない”ことが生き残りの鍵
バフェットの貿易観は、そのまま投資にも当てはまります。
誰かを出し抜こうとせず、自分の得意なことに集中し、信頼と協調を大切にする。
アメリカに再び生まれたい──バフェットが信じる国の本質と未来
要点
バフェットは「今また生まれ変わるとしても、アメリカを選ぶ」と語り、課題を抱えながらもアメリカの底力と進化を信じていることを示した。
🗨️ 質問(翻訳)
「あなたは長年、アメリカの追い風と回復力を信じてこられましたが、
現在、アメリカは重大かつ革命的な変化の中にあります。
一部の投資家は“アメリカ例外主義”に疑問を抱いています。
あなたの見解では、投資家はアメリカ経済について過度に悲観的になっているのでしょうか?
それとも、アメリカは新たな視点から再評価されるべき段階に来ているのでしょうか?」
バフェットの回答(翻訳)
「アメリカは常に“重大かつ革命的な変化”の中にありました。
私たちは農業社会から出発し、すばらしい理念を掲げたものの、その実現には長い時間がかかりました。たとえば、“すべての人間は平等に生まれる”と宣言した一方で、
黒人を5分の3として数えるような矛盾を抱えていました。
憲法には男性代名詞が20回も使われているのに、女性代名詞はゼロ。
女性に選挙権が与えられたのは1920年の修正第19条によってです。つまり──我々は常に変化の中にあり、未完成な国家であり続けてきた。
それでも私は、1930年にアメリカで生まれたことを人生最大の幸運だと思っています。」
💬【“今また生まれるとしても”アメリカを選ぶ理由】
「私が今、再び生まれ直せるとしたら、子宮の中で交渉してでもアメリカを選ぶと思います。
世界の出生のうち、たった3%がアメリカで起きています。
私はその幸運な3%に選ばれたのです。
そして、白人男性として生まれたこともまた、非常に幸運でした。私たちは不況、戦争、原爆、政治的混乱、あらゆる試練を経験しましたが、
アメリカはそのたびに復元力を示し、進化してきました。今の状況を見て“問題が多すぎるからこの国は終わりだ”と考える必要はありません。」
解釈:バフェットは“理想”ではなく“進化”としてアメリカを語っている
このやり取りから見えてくるのは、バフェットが「アメリカを理想的な国」と言っているのではなく、
“進化し続ける力を持った国”として信じているという長期的な視点ではないでしょうか。
1. 問題があるからこそ変化できる
- アメリカは多くの矛盾と課題を抱えている国である
- しかし、課題を認識し、議論し、変えていく土壌があること自体が価値
- 「未完成であること」が、むしろ未来を拓く前提になっている
2. 「選ばれし国」ではなく「幸運を最大化できる国」
バフェットは“アメリカ例外主義”を信じているのではありません。
むしろ──
- アメリカに生まれたことが偶然だったことを深く自覚している
- だからこそ、その幸運を活かすために「学び、働き、機会をつかむ」必要がある
- これはアメリカ人だけでなく、全ての人にも当てはまる普遍的な哲学です
3. 投資先としてのアメリカの“回復力”を信じる
- 過去の大恐慌、戦争、テロ、リーマン危機、コロナなど
──すべての試練を乗り越えてきた国 - 株式市場も長期的には常に新高値を更新してきた
これはつまり、
「アメリカ経済に賭けることは、進化と復元力に賭けること」
という、インデックス投資の根拠と一致しています。
探偵パンダの視点:変化を恐れず、進化の側に立つ
バフェットのこの発言には、個人的にとても勇気づけられました。
「この国はもうダメだ」
「資本主義は終わりだ」
という論調がネットにあふれている中で、
“問題を見たうえで、それでも信じる”という発言には重みがあります。
投資スタンスへの気づき
- 米国経済は、今も「中心」として多くのイノベーションを生み出し続けている
- 政治不信や財政不安があっても、市場全体に投資することで、その進化に乗ることは可能
- 個人投資家としても、「アメリカがダメになる」という前提での極端な行動(全売却など)は慎むべき
私自身も、アメリカは長期的には強い国だと考えています。
確かに現在のアメリカは、政治的分断、財政赤字、国際対立など多くの課題を抱えています。
しかし、そうした問題を直視し、変えようとする意志やエネルギーを持つ人々がいる──それこそがアメリカという国の底力なのだと思います。
批判も多いトランプ大統領のような人物ですら、ある意味で“現状を変えたい”という国民の声の反映だと見ることもできます。
短期・中期的には波乱もあるでしょう。
でも、課題を力に変える国力を信じているからこそ、長期ではアメリカに賭ける価値があると感じています。
総括:安心と学びをくれる、“生きる伝説”
今回のバークシャー・ハサウェイ株主総会を通じて、私が強く感じたのは、
バフェット氏の言葉に触れることで得られる“安心感”でした。
市場の波は大きく揺れ動き、世界情勢も不安定な今。
しかし彼の語るメッセージは、数字や相場の話を超えて、
価値観・思想・人間観に満ちたものでした。
投資についても、通貨リスク、分散の大切さ、長期の視点など実践的な学びがたくさんありましたが、
それ以上に心に残ったのは──
「変化を恐れず、信頼と共存を大切にする姿勢」
「他人を出し抜くのではなく、自分の強みを最大限活かすこと」
「幸運を自覚し、その恩恵を社会にどう活かしていくか」という生き方の哲学
彼の発言には、投資家としてだけでなく、一人の人間としてどう生きるかというヒントが詰まっていたように思います。
そして、94歳になった今も、コカ・コーラの缶を2本携え、4時間の株主総会をこなす姿は、
まさに“生きる伝説”、そして“パワフルおじいちゃん”。
「とにかくすごい」──この一言に尽きます。
今後は、グレッグ・エイベル氏を中心に世代交代が進んでいくことになりますが、
その中でもバフェット氏の哲学はバークシャーに、そして私たち投資家の中にも、
ずっと生き続けていくのだろうと思います。
※当ブログの内容は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
免責事項についてはこちらをご覧ください → [免責事項]





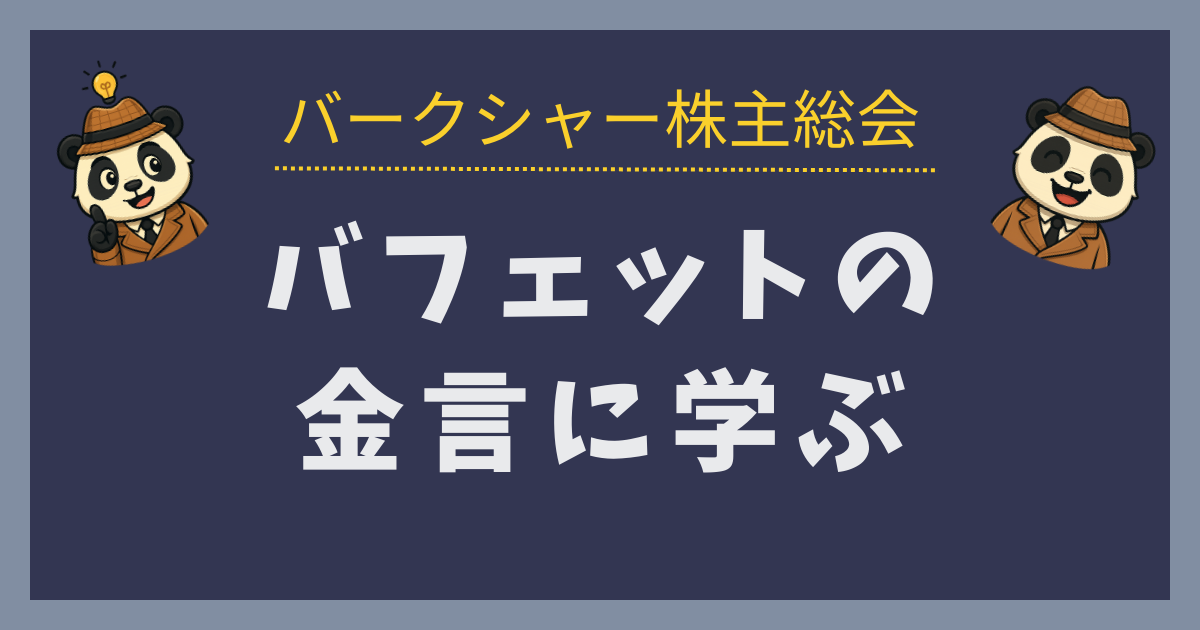
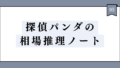

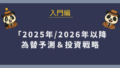
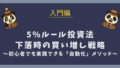
コメント