ミステリー小説の金字塔と呼ばれる「シャーロック・ホームズ」。しかし、今作では推理の範疇を超えた、作者と作品の関係性を問うメタフィクション的な物語が展開されます。不可思議な世界観に酔いしれる一冊です。
タイトル: [シャーロック・ホームズの凱旋]
著者: [森見登美彦]
出版年: [2024/1/25]
【あらすじ】
かつて名探偵として名を馳せたシャーロック・ホームズ。しかし現在は長いスランプに陥り、寺町通221Bに引きこもる日々を過ごしている。
助手のワトソンともどかしい思いをして日々を過ごしていたいたホームズでしたが、ある出来事をきっかけに思わぬ方向に話が進行。スランプから脱却し「凱旋」することはできるのか??
【書評】

ミステリー小説とは一線を画した作風
結論から言えば、本作品は伝統的なミステリー小説とは一線を画しています。不可解な出来事を論理的に解明していくのではなく、不思議なものをあくまで不思議なままに受け入れる姿勢が貫かれているためです。そのため、謎解きを期待する読者には向かない面があるかもしれません。
知的活動よりも人間ドラマに焦点
誰もが一度は聞いたことがある「シャーロック・ホームズ」も、今作では名推理力を発揮することはほとんどありません。家に引きこもってスランプに陥った姿が描かれているのです。活躍するホームズを想像していた方には物足りなさを感じるでしょう。
しかし、アーサー・コナン・ドイルの原作を読んだ人にとっては、パロディー的な要素が随所に散りばめられており、そこに一種の愉しみを見出せる部分があります。
京都とロンドン、二つの異なる世界観
舞台は京都と、ロンドンからかけ離れた土地柄です。原作のおなじみの人物たちも登場しますが、ホームズとの関係性は大きく異なります。
たとえば最大の宿敵ジェイムズ・モリアーティーさえも、ホームズと同じくスランプに陥り、二人で傷の舐め合いをしている始末です。このようなギャップが一種の味わいとなっています。
現実とファンタジーが入り交じる不思議な世界
序盤は、スランプから抜け出してホームズが別の世界で活躍する物語かと思わせますが、徐々に独特の非現実的で突拍子もない出来事が起こり始めます。読者はそのファンタジックな展開に翻弄されることになるでしょう。
全体として、森見登美彦氏の面白さが存分に発揮された作品となっています。ミステリー性は控えめですが、独創的な世界観に浸ることができる一冊です。是非一読をおすすめします。
【考察】

※ここからはネタバレを含みます。
原作シャーロック・ホームズシリーズとのつながり
本作は単なる京都を舞台にしたパラレルワールドの物語ではありません。序盤の第1章から第4章までは、京都版のジョン・H・ワトソンが執筆中の「シャーロック・ホームズの凱旋」という作品を読んでいる設定になっています。
そして第5章以降は、京都のワトソンが体験したロンドン版の世界を舞台に描いています。つまり、本作品には2つの世界が存在しているのです。
- 京都版シャーロック・ホームズの世界(本作品)
- ロンドン版シャーロック・ホームズの世界(ドイル原作のホームズシリーズ)
※ただし、ロンドン版は舞台だけが原作の世界で、登場人物などは異なる仕様となっています。
この2つの世界は、不可思議な空間「東の東の間」でつながっています。虚実が入り交じるこの複雑な構造が、本作を難解なストーリーにしているのです。
物語と作者の関係性が本作の真のテーマ
京都版(本作品)、ロンドン版(ドイル原作)ともに物語の語り手(執筆者)はジョン・H・ワトソンです。ここに重要なヒントが隠されていると思われます。
2つの作品は舞台が違うだけでなく、登場人物同士の関係性にも大きな違いがあります。モリアーティー教授、アイリーン・アドラー、ハドソン夫人など、ドイル版とは描かれ方が異なる人物が多数登場します。
中でもワトソンの妻メアリ・モースタンは大きな違いがあります。
- ドイル版ではメアリは既に亡くなっており、ワトソンとホームズの関係を認めていました。
- 一方の本作ではメアリは生存しており、ワトソン、ホームズの仲を良しとは思っていません。
- さらに、ロンド版の世界に移動したときワトソンは作中でメアリの病気に気づけなかったことを後悔する描写もあります。
つまり、京都の世界は語り手ワトソンが望んだ世界線(贖罪の念も含めて)なのではないでしょうか。ドイル版の現実とは違う、ワトソンなりの理想の世界を作り上げている可能性があります。
言い換えれば、物語の語り手をワトソンに託した森見氏とドイルの思いを反映した作品になっているのではないでしょうか。
またロンドン版の世界に移動した際に出てくるモリアーティー教授とシャーロック・ホームズは同一人物という設定で、世界の終焉(物語の終わり)を望んでいました。これはアーサー・コナン・ドイル自身が望んでいた世界線なのではないでしょうか。
「私が彼(ホームズ)を殺さなければ、私がホームズに殺されていただろう」
とドイル自身も発言しています。
ドイルはホームズシリーズを嫌っていたようで、一度はホームズを殺して終わらせようとしましたが、ファンの熱い要望で続編を書かざるを得なかった経緯があります。作中に登場したモリアーティー教授が「私は作者の代理人なのだ」と言うように、ドイルの思いを投影していたのかもしれません。
本作品の真のテーマは「物語と作者の関係性」なのではないでしょうか。
小説は架空の世界と架空の人物によって生み出される物語です。すべては作者によって創造されたものなのです。作者には望み通りの世界を作れる”絶対的な力”があります。
しかし一度作品ができると、作り手である作者よりも登場人物の活躍や物語そのものに目が行きがちで、作者自身の思いがないがしろにされてしまうこともあるかもしれません。
ホームズシリーズは優れた作品ですが、ドイルが望んだ世界線を描けなかったという面では、不遇な作品とも言えるでしょう。私たち読者は、物語の結末だけでなく、作者への敬意と感謝の気持ちを忘れずにいることが大切なのかもしれません。
本作品はこのように小説の作者と物語の関係性を示唆していたのではないでしょうか。
最終場面でワトソンとヴィクトリア女王の会話の中にこんな言葉がります。
『ロンドンは確かに実在したのです。むしろこの世界のほうが幻にすぎなかった。もしあなたたちが無事に帰ってこなかったら、すべて夢のように消え去っていたことでしょう』
『私たちは見守ることしかできないのですから』
シャーロック・ホームズの凱旋 ヴィクトリア女王の発言
これは作者と読者の関係性を比喩的に表現したものともとらえることができます。
本作品の語り手(作者)はワトソンです。そのワトソンが記録したことが絶対的な真実である。その絶対的な権力を思った人に対しての発言だととらえると、解釈も少し変わってくるのではないでしょうか。
私たち読者は作者が作り上げた世界(物語)を見届けることはできるが、決して介入することはできない。作者が作り上げた世界をありのまま受け入れ、物語を見守る(楽しむ)ということ。
作者が物語を書くことができない、書きたくないという思いがあれば、それが真実であり、過度に期待してはいけないのではないでしょうか。
作者なくして物語はありません。SNSなどで作品を語る際も、その点を意識する必要があるのではないでしょうか。
※正直ここまでいろいろ記載してきましたが、何が真実で、何が偽りなのか正直わかりません。一個人の考えと思って読んでもらえると幸いです。
【個人的な意見・感想】
私は海外ドラマ版シャーロック・ホームズの吹き替え声優の声でホームズのセリフが脳内再生され、とてもしっくりきました。一見全く違う世界観の京都とロンドンですが、不思議とこの作品を読むとなぜかしっくりくるのです。さすが森見氏の作品です。
森見作品に触れる機会はあまりありませんでしたが、京都を舞台にした青春作品や、嘘と現実が入り交じるファンタジー作品が多いようです。本作はいわゆる森見ワールド全開の作風で、ドイル原作ホームズを知る者からしても非常に面白い出来でした。
パラレルワールドのホームズ作品の中でも個人的にはトップクラスの出来で、大変楽しめました。ホームズシリーズでは描かれなかった空白の時を、作者と読者の気持ちに寄り添いながら新しい視点で楽しませてくれた森見氏に感謝です。またドイル原作を読み返したくなりました。
【総評】
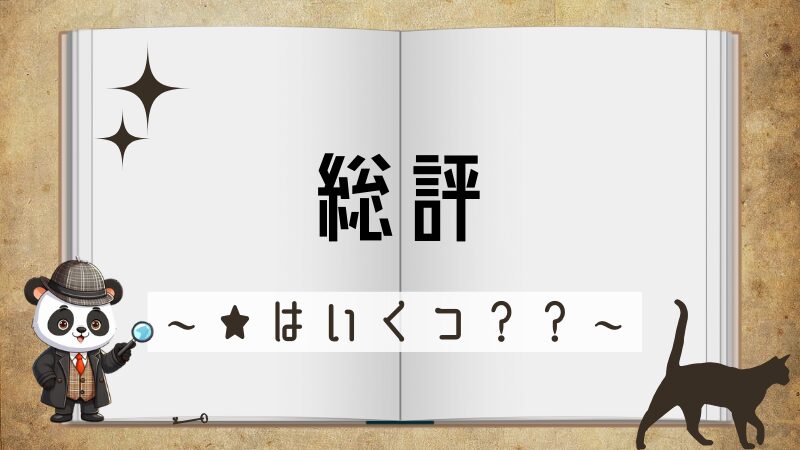
本作品は、伝統的なミステリー小説の枠を超えた、作家と作品の関係性を問うメタフィクション的なファンタジー要素満載な物語でした。不可思議な世界観に酔いしれながらも、物語の核心に作り手である作家の思いが隠されているのが面白い点です。
森見登美彦氏の独創的な発想と筆力が光る傑作で、シャーロキアンにもおすすめできる作品です。ぜひ一読されることをお勧めします。






コメント